◇不動産相続コラム(番外編)【前編】登記簿に残る家督相続◎土地が語る家族の記録◎
※本稿は、筆者が自身の相続手続きを進める中で経験した事例をもとに構成しています。
🏡登記簿が語る家族の記録──家督相続の一行に込められた物語
土地の相続手続きを進める中で、登記簿に目を通していた私は、ある一行に目を留めました。
「家督相続により○○○○(曾祖父)が○○○○(高祖父)から取得」
それは、今から数世代前の相続が、かつて存在した「家督制度」のもとで行われたことを示す記録でした。
(※家督制度は旧民法により明治31年から昭和22年まで規定され、戦後の日本国憲法施行に伴い廃止されました)
🏞山間の家から農村へ──家の移築と本籍地の記憶
私の親族は、山間部に位置する集落に住んでいました。
1970年代頃、山間部の小学校が廃校になるタイミングで、家を農村部へ移築したようです。
しかし、多くの親族の本籍地は今もその山あいの集落に残っており、登記簿の記載からその場所を特定することができました。
このような記録は、単なる法的履歴ではありません。
それは、自分のルーツを辿る手がかりであり、土地の背景にある人のつながりや家族の歴史が、静かに浮かび上がってくる瞬間でもあります。
📜家督制度が映す時代背景と家族の選択
登記簿に残る「家督相続」の記載は、制度上の履歴であると同時に、土地を守り受け継いできた家族の選択と歴史を映し出すものです。
・明治期に土地を取得した高祖父
・家督相続による曾祖父への名義変更
・共有名義や分筆が一度も行われていない──長男から長男へと単独で継承されてきた背景
家督制度では、家の維持を重視し、財産を分割せずに一人の後継者(多くは長男)に集中させることが一般的でした。
その名残か我が家では、土地や建物は兄弟姉妹で共有されることなく、代々単独名義で受け継がれてきたようです。
🧭登記簿が導く家族史──一行の重み
不動産会社に勤めていると、登記簿の読み方や制度の変遷にはある程度慣れています。
しかし、自分の家の登記簿を見たとき、そこに記された一行の履歴が、思いのほか重く感じられました。
「この土地は、誰が守ってきたのか」「なぜこの人が継いだのか」
登記簿を読み返すうちに、これまで意識してこなかった家族の歴史や、自分がその流れの中にいるという感覚が、少しずつ輪郭を持ちはじめました。
まさか高祖父も100年以上のちに結婚して苗字が変わった玄孫が相続の手続きをするとは思いもしなかったでしょう。
このような記録は、単なる手続きの一部ではなく、家族の記憶をつなぐ静かな証人です。
つづく
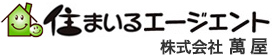
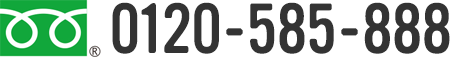

 土地物件
土地物件 戸建物件
戸建物件 マンション物件
マンション物件 事業用物件
事業用物件