◇不動産相続コラム(番外編)【後編】相続人調査と家系図◎広がる血縁と相続観◎
※本稿は、筆者が、自身の相続手続きを進める中で経験した事例をもとに構成しています。
🧾 相続人調査と家系図
相続登記や遺産分割協議を行うには、誰が法定相続人かを明確にする必要があります。
そのためには、以下のような情報を収集・整理します
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・兄弟姉妹、甥姪などの続柄の確認
・代襲相続の有無
・相続関係説明図(家系図)の作成
この作業は、法務局への登記申請や、関係者間の合意形成に不可欠な作業です。
🧠 現代の相続と人のつながり
現在では、法定相続制度のもと、兄妹で財産を分け合うことはごく自然なことです。
共有名義で相続するケースも多く、家族それぞれの立場や思いを尊重した柔軟な分割が行われています。
それは、家族のかたちが多様化した現代において、公平性と合意形成を重視する相続のあり方とも言えるでしょう。
登記簿に記された一人の先祖から、世代を重ねて枝分かれした家族の数は、驚くほど多くの人が、今の自分に関わっていることを教えてくれます。
実際、家系図をたどっていくと、高祖父から数えて約120人ほどの血縁者が存在していると考えられます。
その広がりは、相続を「自分だけの問題」ではなく、家族全体の歴史の一部として捉える視点を与えてくれます。
🪞 相続は「記録の継承」であり「自己理解」の機会
家系図の作成は、法的手続きの一環でありながら、自分のルーツを可視化する副次的な価値を持ちます。
それは、土地の背景を理解し、合理的な判断をするための重要な情報でもあります。
・どのような経緯で土地が受け継がれてきたか
・どの親族が関与してきたか
・今後の管理や活用にどうつなげるか
📌 まとめ:登記簿は相続の「地図」であり、記憶でもある
・登記簿に残る家督相続の記録は、家族の歴史の一部
・相続人調査には戸籍の収集と家系図の作成が不可欠
・高祖父の記録をたどることで、自分の位置づけが見えてくる
・相続は、未来への備えであると同時に、過去とのつながりを確認する機会でもある
登記簿に記された一行の履歴が、自分がどこから来て、何を受け継いでいるのかを教えてくれることがあります。
それは、相続という手続きを、人間的な営みへと変えるきっかけになるだけでなく、
これから自分が何を守り、どう次の世代へつないでいくのかを考える出発点にもなるのです。
相続した土地は、放置すれば固定資産税の負担や資産価値の低下につながることもあります。
しかし、適切な活用や売却によって、未来の資産へと生まれ変わらせることが可能です。
私たち住まいるエージェント株式会社萬屋では、倉敷・岡山エリアを中心に、土地の売却・有効活用・相続対策など、
不動産にまつわるあらゆるお悩みに寄り添い、最善のご提案を行っています。
・賃貸アパートや駐車場としての活用
・相続した土地の売却と現金化
・空き家対策や収益化のプランニング
・法的手続きや節税のアドバイス
不動産は「資産」であると同時に、「記憶」でもあります。その価値を未来へつなぐために、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの大切な土地に、新しい可能性を。住まいるエージェント(株)萬屋が、心を込めてお手伝いします。
おわり
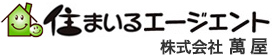
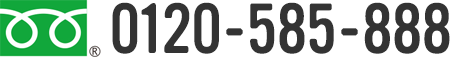

 土地物件
土地物件 戸建物件
戸建物件 マンション物件
マンション物件 事業用物件
事業用物件